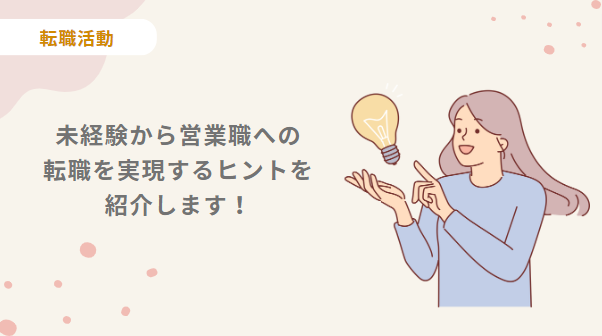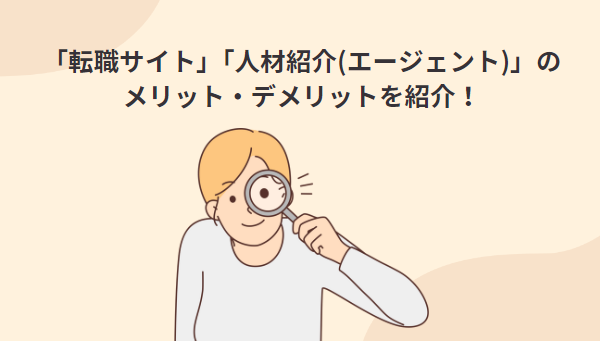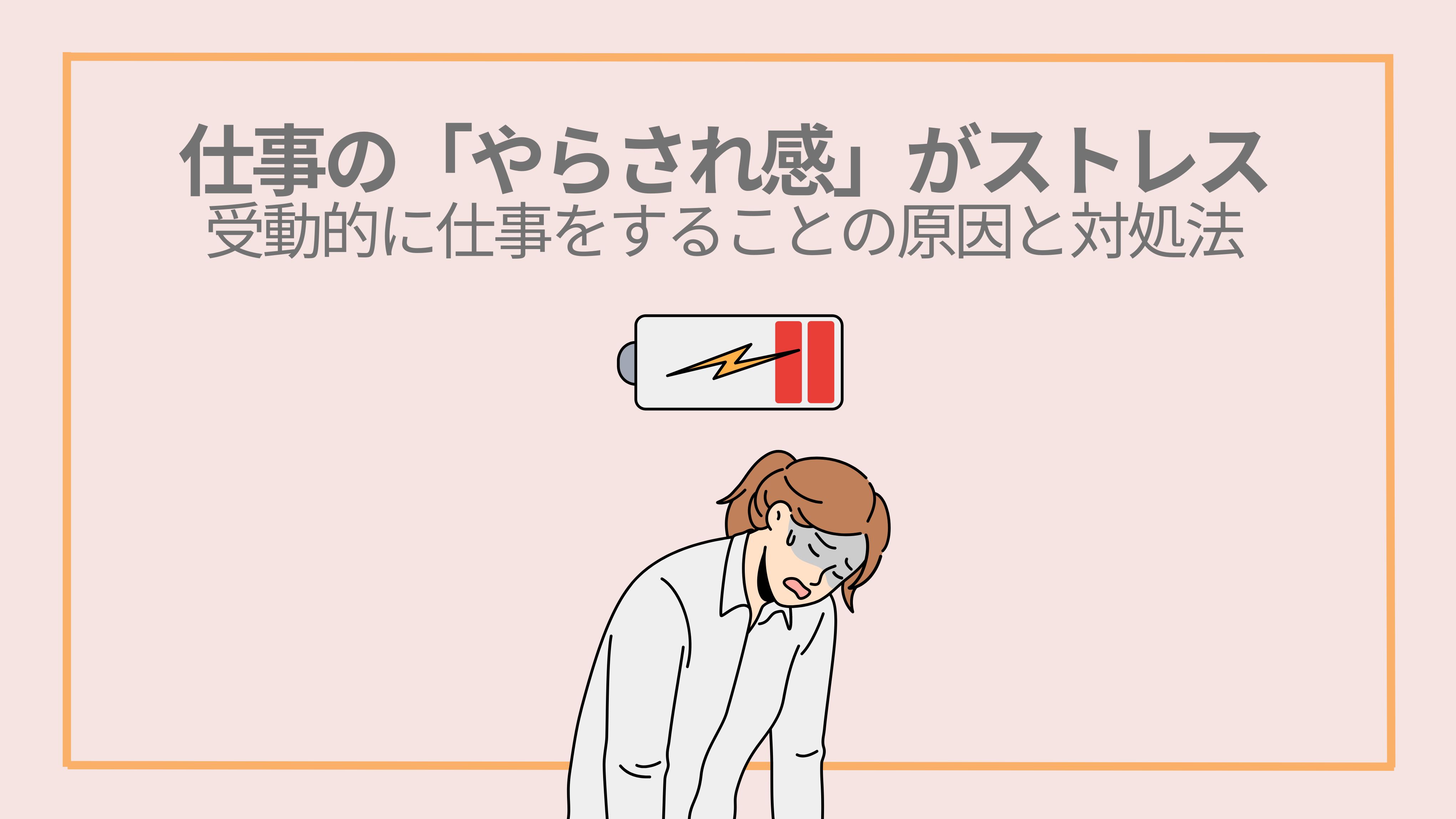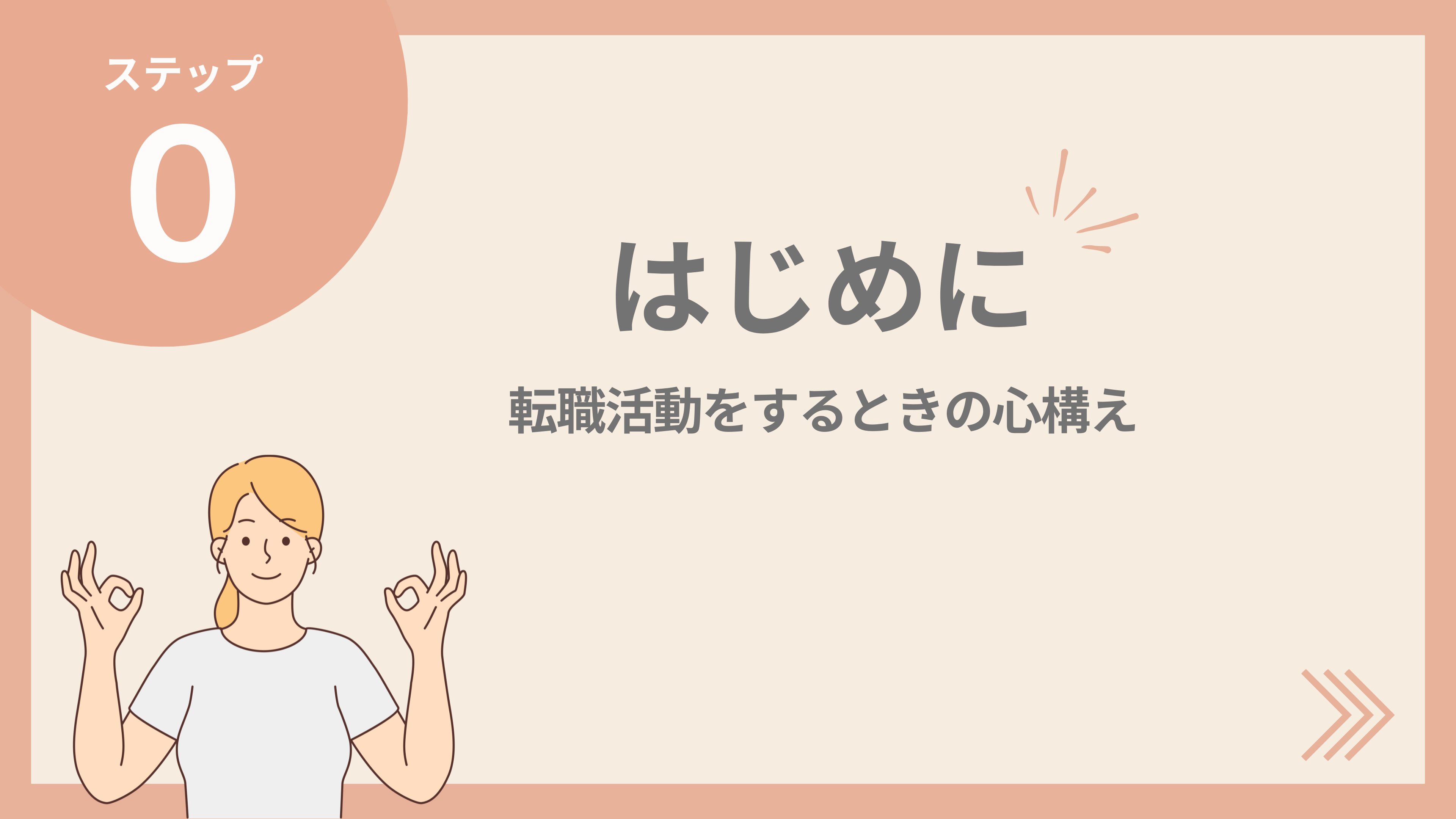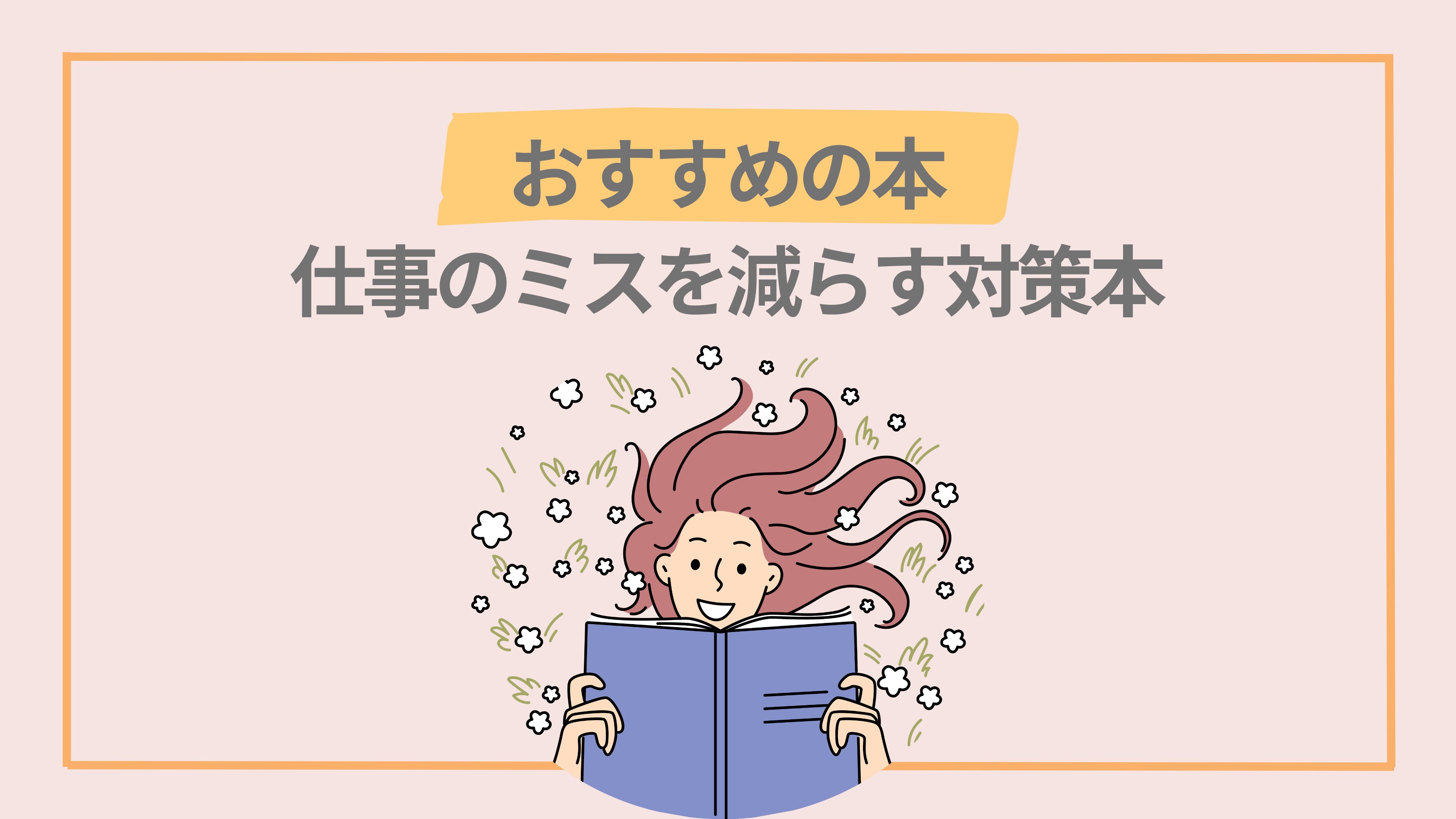「仕事で責任を取りたくない!」ー責任感がない人の特徴と解決策を紹介
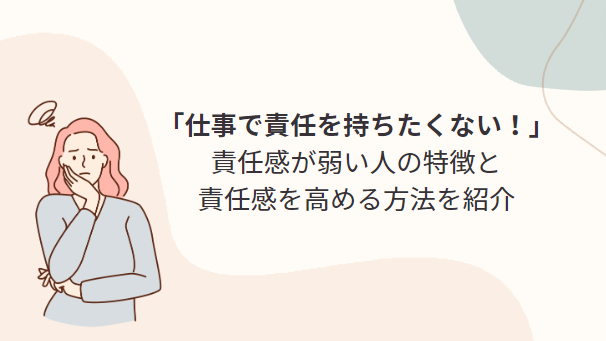

責任感がないのか、責任がある仕事を受けたくないです。
ただ、年次的に責任ある仕事を任されそうで……。
責任感を持てるようになるにはどうしたらよいですか?

そうなのですね……!
では、今回は責任感が弱い場合の解決策を紹介していきましょう。
この記事では、責任感が弱い人の特徴と責任感を高める方法を紹介します。
この記事を読み終えると特徴を客観的に見たうえで、自分らしい解決方法を検討していくことができるでしょう。
この記事が、仕事を上手くいかせる一助になれば幸いです
この記事を監修した人

名前
かに(一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ)
経歴
“3か月でごきげんに働くわたしになれる”
がんばりやさんがごきげんに働く道のりを紹介する
「かにちゃんのごきげんジョブチャンネル」を運営
・人事系研究員(専門:20~30代の職場活躍・職場コミュニケーション実践)
・大手転職エージェント(企業向け採用コンサルティング・求職者向け転職アドバイス)
・個人向けコーチング・カウンセリングの提供
美味しいごはんと温泉が好き
この記事を監修した人

名前
かに(一般財団法人生涯学習開発財団認定コーチ)
経歴
“3か月でごきげんに働くわたしになれる”
がんばりやさんがごきげんに働く道のりを紹介する
「かにちゃんのごきげんジョブチャンネル」を運営
・人事系研究員(専門:20~30代の職場活躍・職場コミュニケーション実践)
・大手転職エージェント(企業向け採用コンサルティング・求職者向け転職アドバイス)
・個人向けコーチング・カウンセリングの提供
美味しいごはんと温泉が好き
責任感が弱い人がとりがちな行動
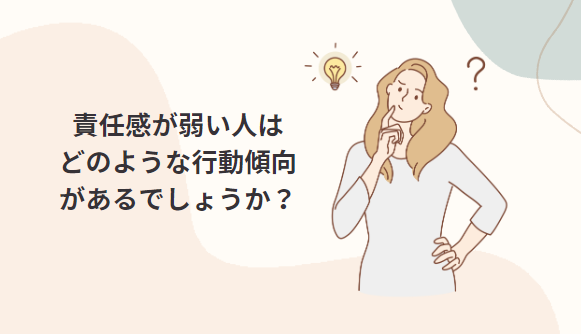
不安や恐怖から逃げがち
責任感が弱い人は、不安や恐怖から逃れるために責任を放棄することがあります。
不安や恐怖の背景には、失敗することや批判されることへのリスクがあります。
特に過去に大きな失敗経験している場合は、経験がトラウマとなり、再び同じような状況に陥ることを避けがちです。
不安や恐怖を避けることは生存本能としてあることです。
もし自分が一歩成長したい、現状を変えたいと思うとき、乗り越える必要が出てくるのです。
私も初めてのことだったり、自分の実力以上のことをするとき、不安や恐怖を感じます。
ですがそのような経験で大きく成長できることが分かっているので、怖さを乗り越えて向き合うようにしています!
他者のことまで考えられない
自分に余裕がないなどの理由でいっぱいいっぱになってしまい、他者の感情や状況までを考えられない可能性があります。
他者のことを考える余裕がないので、自分の行動が相手にどのような影響を与えるかをイメージできません。
すると自分の行動が原因で、両者の間で問題も増えますし、起こった問題を自分で何とかすることができず、結果として責任を取ることを避けがちです。
環境や他者への依存が大きい
責任感が弱い人は、環境や他者へ依存している可能性があります。
環境や他者への依存とは、自分の行動や決断が、自分ではなく周囲の状況や他者の意見に大きく左右されることです。
周囲に依存しているとは、常に誰かの指示や助けを求め、自分で責任を取ることを避ける傾向があります。
仕事でも、上司や同僚に頼りすぎることで、自分の責任を果たす意識が薄れてしまいます。
依存状態の中では、自己決定の機会が少なくなり、責任感を育てる経験が少なくなってしまうのです。
自分の力で問題を解決することの重要性や喜びを感じるチャンスが得られなくなってしまうので、もったいないことです!
向き合い改善していくことをおすすめします。
責任感が弱い人の心理
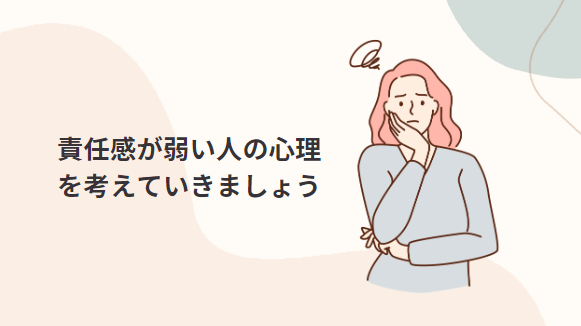
期待に応える自信がない
責任感がない人の中には、自分への無力感を強く抱き、期待に応える自信がない場合もあります。
無力感を持つは「どうせ自分がやっても意味がない」「自分の力ではどうにもならない」と考えがちです。
この状態に陥ると、自分の行動が結果に影響を与えるという感覚が失われ、責任を持つという意味や価値が感じられなくなります。
言われたことはしっかりやるけど、正解のないものを責任をもって「何とかやり切る」ことからは逃げたいと感じている人も多いです。
育った環境の影響
責任感がない人の心理には、育った環境が影響していることがあります。
子どもの頃に誰かが何でも代わりにやってくれる環境だと、自分で責任を取る経験が少なくなります。
これにより、責任について考えたり学んだりする機会が得られず、責任に対するハードルは高く感じるでしょう。
一方、厳しく指導され失敗を恐れるような環境で育った場合も、責任を避ける傾向が強くなります。
自分を守りたい気持ち
責任感がない人の中には、自分を守りたい気持ちが強く働いている場合があります。
自分を守りたい気持ちとは、例えば精神的なストレスや不安を避けるたいという反応です。
ストレスや不安が起きるような負荷がかかることは無意識に避けがちです。
自分を守りたい気持ちを持つことは、精神的には安定感をもたらし有効に働くこともあります。
しかし、今以上の成長を求めたり、違う経験をしたりするときには足かせになる可能性も高いでしょう。
責任感を高める方法

自分のよい面もきちんと見ていく
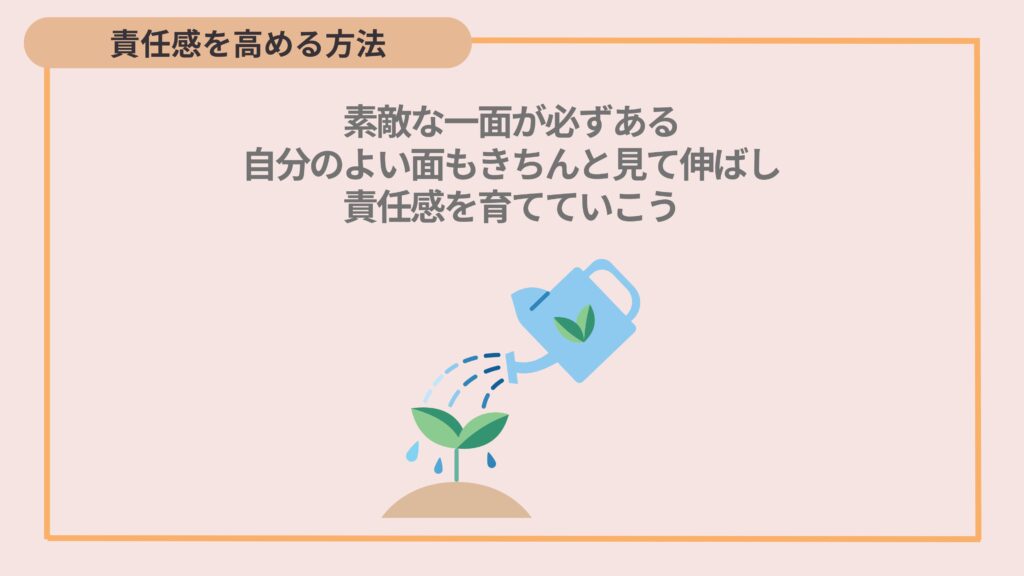
自分のよい面もきちんと見ていくことは、責任感を育てる重要なステップです。
「自分なんて何もない」「何の影響力も持てない」などと自分を否定していると、いつまでも自分の責任で物事を動かしていく気持ちになりません。
イマイチの面もあるかもしれませんが、それと同じくらい、いやそれ以上ステキな面を持っています。

自分を否定する要素を100個出す人は、100個肯定する要素を出してください。
否定する要素を裏返しで考えると楽です。
例:「うるさい」→「明るい」「元気」など
また、信頼できる友人や同僚からよいところを見つけてもらってください!
フィードバックをもらうこと自体とても嬉しいですし、自分がどのように見られているかを理解しやすくなります。

何度も繰り返すたびに、自分のステキポイントが見えてきて、行動する自信がついてきます。
できることを増やしていく
できることを増やしていくことも大切です!
小さなことから仕事にまずは関わって、自分が出来ることを増やしていくと、そのことへの関心が徐々に高まり、責任の気持ちも生まれてきます。
また、できることを増やしていれば「責任を持って物事を進めたい」と自分から思ったものに出会ったときにもスムーズに責任を果たすことができるでしょう。

小さな積み重ねが重要です!
自分の「責任」を意識する
ぜひ、職場の関わる人とコミュニケーションを取り、自分の期待を確認してみてください。
自分の役割や期待されることを明確に理解することで、自分が持つ責任の意識が芽生えてきます。
責任感は、自分で意識しないと持つことができません。
一方で、本質を理解したり周囲の思いに触れたりすると、当事者意識が生まれ、責任感が湧いてきます。

関わる人と「なぜやるのか?」「何を大切にしているのか?」などの意見交換をするのもおすすめです!
ストレス管理やメンタルケア
責任感を持って物事を進めることは、エネルギーが必要です!
心身ともにある程度の負荷がかかるでしょう。
効果的に疲れを解消していくために、ストレス管理やメンタルケアは非常に大切です。

まずは自分のベースを整えることで、物事にブレず向き合うことができます。
ロールモデルを見つける
責任感を育むためには、ロールモデルを見つけることも効果的でしょう。
ロールモデルとは、自分が目標とする人や行動のお手本となる人のことです。
職場や身近なコミュニティでもよいですし、なかなか見つからない人は専門家やYouTuberなどメディア上で参考にしている人でもよいかと思います。
自分が迷ったときや逃げてしまいそうなときに「ロールモデルの○○さんだったら、どんな行動をとるかな?」「どんなことを言うだろう?」と想像してみてください。
今回は、責任感が弱い人の特徴と責任感を高める方法を紹介してきました。
ぜひ、特徴を客観的に見たうえで、自分らしい解決方法を検討してみてください。
この記事を読んで、少しでも仕事の状況がよりよいものになっていくことを、心からを祈っています